


【イベントレポート】澤円氏と考える 人生100年時代における「マネジメント」のキャリア
公開日:2024/01/29 / 最終更新日: 2024/02/05
昨今、働く人一人ひとりの価値観が多様になり、働き方やライフスタイルを選ぶこともできるようになりました。組織の中でチームを取りまとめる「マネジメント」のあり方も変化し、マネージャーのキャリアも多様化しています。今の時代におけるマネジメントには、いったいどのようなスキルや価値観が求められるのでしょうか。
今回はJAC Digitalのアドバイザーであり、自身もITエンジニアから世界的外資IT企業の業務執行役員に就任し、現在は独立してキャリアに関するセミナーを数多くこなす澤円氏に登壇いただき、澤円氏自らが実践した1on1マネジメントの経験や、「これからの時代に求められているマネジメントとは何なのか?」などについてうかがい、あらためてマネジメントについて考えていきます。
※ 本記事は2022年7月27日にJAC Digitalが開催したオンラインイベントを一部抜粋・再構成したものです。
目次/Index

意識のアップデートは靴紐を結ぶようなもの
2020年にコロナ禍がやってきてから、「仕事がオンラインに変わって、やりにくくなったのでは?」とよく聞かれます。オンラインとオフラインの比較はマネジメントの文脈でもよくあがる話題ですが、電車と飛行機を比べるようなもので意味がないし、議論にならないと考えています。インターネットが登場した時と同じくらいの衝撃で、人々の意識や社会の状況にリセットがかかったわけです。コミュニケーションのあり方が変わったことでマネジメントのやり方も変えていく必要があります。
インターネット黎明期には「コンピューターと向き合っていると遊んでいるように見える」と言っている人たちがいました。そう話していた人たちは今、スマートフォンを使うのに四苦八苦していたりします。分からないままにしておいたツケが回ってきただけの話です。今マネジメントに関わっている人たちも、新しいものについていけないだとか、自分の仕事じゃないなどと言っていると、当然同じことが起きるでしょう。新しい働き方に対応することは、靴紐を結ぶことと同じレベルだと言えます。つまり、自分でやることであって、人にやってもらうことではないし、やらないと危ないということです。
人々の意識や社会の状況にリセットがかかったわけですから、マネージャーとしてのマインドセットのアップデートも絶対に必要です。
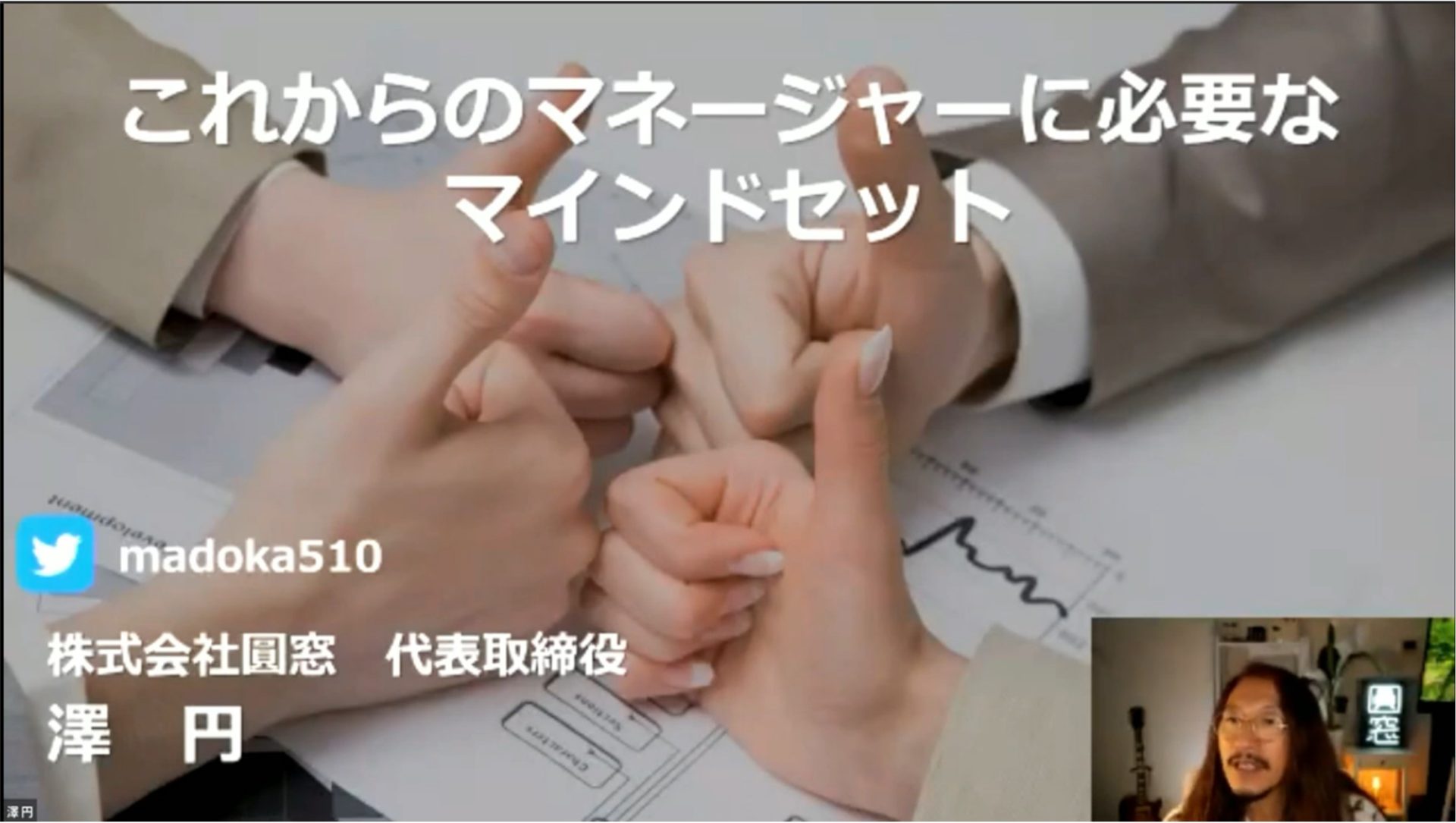
報告と連絡は自動化し、未来の相談に時間を使う
サラリーマンとして大事な「報告・連絡・相談」の話をしましょう。この三つは時系列になっています。報告は過去のこと、連絡は現在のこと、そして相談は未来のことです。マネージャーは報告や連絡のためのミーティングをせず、未来の相談に時間を使ってほしい。なぜなら、報告と連絡はデジタルツールの力で自動化できるからです。管理は機械の方が得意ですから、人間がやる必要はありません。管理はどんどんAIに移行して、マネージャーは積極的に相談にのってください。
報告には「不変性」が求められ、内容が変わらないことが大切です。ここが変わってしまうと、粉飾決算などのトラブルにつながっていきます。連絡には「即時性」が求められますが、相手の集中力を途切れさせる電話は最悪のチョイスだと私は思っています。失われた集中力が元通りになるには15分以上の時間がかかるというレポートもあります。
相談には「人間性」が問われます。人間性を知るための飲み会という行為自体は否定しませんが、全員が行けるわけでもないし、全員が行きたいわけでもありません。就業時間の後でどうにかしようと考えている時点で、マネージャーとしてはイマイチです。仕事なのだから、就業時間中に仕事を通じて人間関係を構築しましょう。
社会貢献の仕方をメンバーと本気で考える
会社は所属する全員が社会に貢献するために自分のリソースを使う場所です。経営者は全体像を見て会社の位置付けを俯瞰しており、一般社員は解像度の最も高い世界が見えています。マネージャーはどういう仕組みで会社組織が動いているのか、内部構造を認識することが重要です。社会貢献を実現するという目標に対して、それぞれの人が見ている世界に興味を持ち、通訳していかなければなりません。
マネージャーに持ってほしいマインドセットは、教わる勇気を持つことです。チームメンバーに先生になってもらい、教わることも仕事だと考えてください。そして、黙って任せて、結果に対して責任を持つ。これがマネージャーの格好いい責任の取り方です。最悪なのは、口は出すけど予算やリソースを提供しないこと。文句ばかりを言って自分の権限を行使しない人は、マネージャーには向いていません。
「自分は仕事を通じて、世の中をどうやってよくしていきたいのか?」をメンバーと一緒に考え、メンバーに全力疾走してもらうための環境を先回りして整えるのがマネージャーの仕事です。説明がつかないことやいろいろな理不尽も含めて、綺麗ごとを本気でやろうと言ってチームを引っ張っていく。他人の人生に対しても責任を持つわけですから、お金のためのライスワークからは卒業する必要があります。
マネージャーがしてはいけないこと
マネージャーたる者、「できない理由」は探さないでください。マネージャーができない理由を探し始めたら、みんなが後ろ向きになってしまいます。PDCAのPの割合はできる限り小さくして、やたらと計画を求めるのではなく、まずやって、何か問題があったらチェックする。顔も名前も知らずにリモート面談だけで採用を決めた会社もあるくらいですから、やろうと思えばいろいろなことができるわけです。
メンバーとの競争も、絶対にやってはいけません。評価する権限を持っているだけでも大きなプレッシャーをかけるので、その状態で競争するのはフェアではありません。また、怒りで相手をコントロールすることは、心理的安全性を壊すことになります。マネージャーだからといって持論に引っ張り込むのは反則ですし、チームをよくすることに寄与しないのです。
優秀なプレイヤーを昇格・昇給させるためには、チームを持たせることがセットであるという制度の会社はかなり多く、これが諸悪の根源だと思っています。僕は「マネージャー名誉職問題」と呼んでいるのですが、向いていない人にマネージャーを任せるのは危険ですし、マネージャーだから偉いというわけでもありません。「ただの係である」というマインドを持てないマネージャーには、人が付いていかなくなります。
1on1で心理的安全性を確保する
マネージャーの最も大事な仕事は1on1です。一対一の個人面談を、ほかの人が誰もいないところで、就業時間中に実施してください。僕がマイクロソフトにいたときには、1on1をしないことはペナルティに値し、マネージャーとして不適格と評価される仕組みになっていました。ちなみに僕は年上が多いチームのマネージャーを務めていて、何かを教えたりコーチングをしたりするのではなく、自分は何も教えられない、自分は教わる立場だという姿勢を徹底し、あなたを売り込ませてくださいというスタンスで接していました。
1on1での絶対条件は、心理的安全性を整えることです。1on1の場でも、チームに戻って仕事をするときにも、ここで仕事をするのは安全だと思ってもらう。今の時代、恐怖で縛ろうとしたところで、ほかにもっとよい職場があることがわかっているので、優秀な人材をつなぎ止めることはできません。相手に興味を持ち、話を聞くことによって多くの情報を得てください。
話を聞くときには、事実と所感を分けなくてはいけません。相手が曖昧な表現を使うようであれば、もっと具体的に話すよう促すことも必要です。数字を使って具体的な会話やレポートにしてもらい、チームメンバーの見ている解像度の高い世界に近づきましょう。
何か問題が起きたときに、個人を「なんで?」で問い詰めてはいけません。自分の思考に「なぜだろう?」と問いかけるのは大いに結構ですが、人に対しては「なんで?(Why)」と聞かず、「何があったのか?(What)」を説明してもらうようにしてください。Whyの矢印は個人に向けられていますが、Whatは矢印が「もの」に向いているので、その問題にチームで取り組めます。「何があったのか?」と問いかける習慣づけをして、さらに「どうやったら助けられる?」を口癖にすれば、心理的安全性をプレゼントすることになり、チームのメンバーがどんどん情報を持ってきてくれるようになります。
質疑応答
Q. マネージャーではない人がマネージャーになるためには何が必要でしょうか。
マネージャーを作るプロセスは組織によって違うので一概には答えられませんが、マネージャーでない人にもマネジメントのマインドセットは必要です。人のために先回りして障害をなくしたり、Whyで聞かずにWhatで考えたりというマインドを持って、それに従った行動ができていれば、スッとマネージャーのポジションが降ってくるのではないでしょうか。
Q. フィードバックを繰り返しても届かないメンバーにはどのようなアクションを取りますか? 辞めさせるという選択肢も検討するのでしょうか。
何かが達成できないという状況には、与えられているポジションとその人のポテンシャルがマッチしていない状態が背景にあると思います。こうした役割との不整合=ロールアンマッチが起きているときには、コンバート(転換)が一つのアプローチになりますが、その判断には評価軸が必要です。評価軸に照らして、あなたの能力がこれに達していないから、真価を発揮できる別のポジションを一緒に探しましょう、と働きかけるのがマネージャーの仕事になります。
Q. 1,000名程度の企業で部長職をしています。私の下には3チームあり、それぞれのチームのマネージャーとは定期的に1on1を実施していますが、個別のメンバーとは接点を持てていません。澤さんはこのような状況では、どのようなことを意識してマネジメントするでしょうか。
1on1をするのはマネージャーの仕事なので、そこはお任せでもいいと思います。もし追加で実施するとしたら、自分の予定表をオープンにして、「この時間なら一緒にお茶を飲めるよ」と伝え、カジュアルな1on1として相手に時間を選んでもらうといった緩い方法がいいかと思います。
Q. パラシュート人事でマネージャーとして新しい組織に入った場合、最初に気をつけなければいけないことはありますか?
前の職場やこれまでの職場、私が学んだことは……と自分の価値観を押し付けると一発で嫌われます。この場所ではどのようにやってきたのか?と聞くことで、その人たちが過ごしてきた時間に対して興味を持つことが重要です。内容が正しくなかったりイマイチだったりしても、まずはその場で培われてきたものを尊重してください。
Q. マネジメント業務や同僚との話の中で、プライベート寄りの問題に巻き込まれ、心理的な負担を感じてしまうことがあります。
ここから先はプロの領域だと感じたら、プロに相談しなさいというアドバイスに切り替えてください。自分ですべて相談に乗るのではなく、医者や弁護士、会社のカウンセリング部門に相談してもらうなど、バトンを渡すお手伝いをすることが大事だと思います。むしろ、プロに任せなければいけないレベルでマネージャーが出てくることの方が問題です。
Q. 外資系に転職して初めて外国籍メンバーのマネジメントを任されており、価値観や考え方の違いなどを痛感しています。多様なバックグラウンドを持つ人のマネジメントで意識していることはありますか?
外国籍や性別などはすべてひっくるめて誤差です。「人は他人のことを何もわかっていない」という前提に立って、まずは自分からオープンになってください。自分の弱みやできないこと、苦手なことなどを自己開示したうえで、相手に興味を持って話を聞いてください。
Q. 一般社員から上司にコミュニケーションを取りづらい場合、相談を受けやすい空気を作るために何かできることはありますか?
これも上司側の自己開示が効果的です。その方法として、テクニカルな話ですが、声は人で距離をものすごく縮めるので、社内向けの音声配信サービスを利用してみるのはいかがでしょうか。声だけの録音なら、動画を撮影するほどハードルは高くありません。インタビューの中で失敗談や若いころの苦労話を聞き出して、社内でシェアすれば効果があると思います。
Q.ライスワークから脱却するための方法や習慣についてのアドバイスをお願いします。
自分のマネージャーとしての価値を知るためにも、外の物差しを持ちましょう。マネジメントはチームごとにまったくアプローチが変わるので、外で活躍できるかどうかを自分で試してみることが重要です。僕はビズリーチの創業当時からメンターをするなど、ほかの会社のお手伝いをすることがライフワークになっていきました。今まで接点がなかったコミュニティへの参加や、イベントのボランティアスタッフなどからはじめてみてはいかがでしょうか。

















