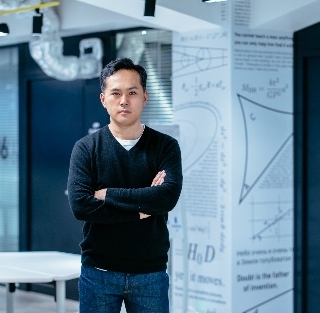オープンイノベーションの落とし穴
公開日:2024/01/30 / 最終更新日: 2024/02/15
目次/Index

大企業がDXを導入する際の選択肢として、スタートアップとの提携がある。業務提携や出資またはM&Aなどを通じて、有望な新興企業の技術を取り込むことで、着実かつ効果的に自社のDXを実現したいと考える企業は多い。
社外から新たな技術を取り込むことで、イノベーションが起きづらい大企業に革新的なビジネスモデルの導入やサービス開発を誕生させる「オープンイノベーション」は、国を問わず多くの大企業が経営の重要課題に掲げるテーマだ。
しかしながら、組織規模も資本の差も大きな両者の提携は一筋縄ではいかない。欧米では旧約聖書に登場する巨人兵士ゴリアテと、羊飼いの少年ダビデに例えられることも多い両者だが、敵対したりお互いの力を誇示したりするのではなく、お互いの強みを持ち寄ることがオープンイノベーションの本質であり原則だ。
そこで今回は大企業が陥りがちなオープンイノベーションの失敗例から、スタートアップとの提携を成功に導く方法を紹介しよう。
バズワードありきの提携
「AIを使って何ができるか知りたいから」など、流行のキーワードに飛びつくような提携は、かなりの確率で失敗する。
少なくともそのキーワードと、自分たちの本業が結びつくまでの距離感や、具体的な導入イメージを理解できなければ、最適なスタートアップとのマッチングどころか実証実験するテーマ選定も難航するだろう。
DXのように一つのテーマの中に、さまざまな技術や機能が含まれる言葉であれば、更に事業との関係性をクリアにする必要がある。例えば、「製造業とDX」と言っても、使う場所が生産拠点かマーケティング活動かでは技術もソリューションも、検討の俎上にあがるスタートアップも全く異なることは、製造業に従事していないビジネスパーソンでも容易に想像がつくだろう。
予算と権限のない組織が窓口になる
スタートアップとの協業を模索する際、多くの大企業が有望なスタートアップの調査や実証実験などの交渉を担う部署を事業部とは別に設置している。しかし、ここに落とし穴がある。
提携先のリサーチと提案だけをミッションとする部門は、本業で稼ぐ事業部との間に溝が生まれやすい。なぜならば、新しい取り組みは企業内の生態系を変えることが往々にしてあり、変えることで不利益を被る部署からの反発が起きることがあるからだ。対面でのセールスをしていた営業部門にインターネット販売を提案したら、どんな反応が起きるか想像するとわかりやすい。
こうした提案を事業部門の内側から行うか外側で行うかによって、実現の確度は大きく変わる。
現場からの跳ね返りが強いと、イノベーション部門は事業に直接貢献できる提案がやりにくくなる。その結果、スタートアップが集まってプレゼンテーションやディスカッションするようなイベントの企画に活動が留まり、数年間の活動で残ったのはイベントの集合写真だけだったという事例も少なくない。
事業に貢献しないことにはオープンイノベーションは成功とは言えず、まして駆り出されたスタートアップも自分たちの売上が増えなければ時間の無駄でしかないのだ。
人事異動で全てが止まる

外資系企業と異なり、日本企業はジョブローテーション制度が根強い。そのため、スタートアップとの協業担当者が異動した結果、引き継ぎがうまくいかず、進めていたプロジェクトがリセットされてしまうという事態が起きやすい。
大企業であれば、組織でカバーして人が変わっても機能するようにするものだろうと考えるかもしれないが、ほとんどの企業においてオープンイノベーションに関する取り組みは前例がない。過去に大学や研究機関、ベンチャー企業と提携した実績はあっても、スタートアップを巡る環境は数年単位で変化する。技術トレンドの変化はもっと早い。
そうなると、担当者個人のコミュニケーションスキルやモチベーションに大きく依存してしまう。まして利益を生むかどうかわからない取り組みともなれば、担当者は多くない。
いくつかのPoCや実証実験が軌道に乗ったタイミングで企業の担当者を異動し、後任になった途端にプロジェクトが止まってしまったと嘆くスタートアップを筆者はいくつか見てきた。
こうした事態に陥らないためには、大企業はスタートアップとの窓口を個人ではなく、チームでカバーするべきだろう。また、実際に事業を協働する事業部門にも担当者を置いたり、キーマンとスタートアップの接点をもたせたりするなどして、一個人に依存しない体制を作ることが重要だ。
スタートアップに不利な契約
スタートアップと大企業の提携で近年問題になっているのが、ごく一部の大企業によるスタートアップ搾取とも取れる行いだ。
公正取引委員会が毎年発表している実態調査報告書には、大企業から知財を侵害された、不平等な取引条件を盛り込まれた、という事例が掲載されている。
「契約書の中に大企業がスタートアップの許可なく特許を申請できる条項を盛り込んだ」
「スタートアップが開発したサービスのライセンスを無期限かつ無償で提供するよう要求された」
「ほとんどは自社で研究するのに,成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる」
こうしたスタートアップや中小企業からの声に、公正取引委員会は中小企業庁や特許庁、経済産業省と連携して厳正に対処すると発表している。海外でも今年1月にアップル社が特許侵害によって、カナダのベンチャー企業に約90億円の賠償を命じる判決が下されているように、巨大企業であっても特許侵害による賠償は起きうる。
利己的な関係に陥らないためには、提携する企業は下請ではなく、協業するパートナーという認識を大企業のトップレベルでも理解することが不可欠だ。スタートアップ側も提携できる先は一社ではないので、不当な条件が提示されれば別の大企業にスイッチするという選択肢もある。目先の利益を先行した結果、提携が破断になり競合他社に市場を奪われたともなれば、その企業におけるオープンイノベーション文化は絶滅したも同然だろう。
大企業だからこそのガバナンスとチームワークが重要

これまでに紹介したような事例を回避するためには、大企業が持つ資産を正しく使うことが重要だ。つまり、一個人に依存せずに組織の事業活動としてスタートアップとの協業を進めること、自社だけが得をするような取引関係にならないよう、ガバナンスに目を光らせることだ。
イノベーションは後になって気付くものであり、目指して実現するものではない。イノベーションを求めて無計画に走り出すという冒険精神ではなく、事業を成長させる機能を社会の中から見出すという骨太な意思こそが、大企業にとっての新たな起爆剤となる。
参考資料:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-yuetsu/index.html
IT業界の転職関連コンテンツ
IT業界の職務経歴書の書き方
- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説
転職サポート サービスの流れ
-
Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。
-
Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。
最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -
Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。
レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。
-
Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。
ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -
Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。