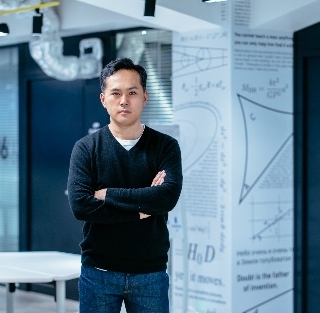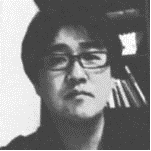金融サービスが多様化し、シームレスにつながるなか、
金融・非金融間のFintech人材流動はより活発に
公開日:2024/01/30 / 最終更新日: 2024/03/18
目次/Index
Fintech関連・金融業界を対象にデジタル領域専門で採用を支援する当社のコンサルタントが、Fintech領域でのDX推進状況と、それに伴うデジタル人材ニーズの変化、採用を成功させるためのノウハウを解説します。
解説者
川野龍
Fintechベンチャーの事業開発・エンジニアなどデジタル人材領域を担当。豊富な実績と経験をベースに、メガベンチャーからスタートアップまで幅広くサポートする。鳥井玄人
主に金融機関を担当し、金融×IT、デジタル領域の採用をサポートしてきた。従来の金融機関におけるIT部門の各職種から、デジタル部門のニーズにまで対応する。※所属部署・役職は撮影当時のものです
Fintech関連・金融業界を取り巻くDXのトレンド

Fintechのキーワードを軸に置いてその関連業界を定義する場合、銀行・証券会社・保険会社など従来からある金融機関、大手〜中堅のWeb系企業でFintech事業に進出したプラットフォーマー、当初よりFintechサービスを主事業に立ち上げられたアーリーフェーズ寄りのベンチャーなどが対象プレイヤーとなります。
新旧さまざまな企業が参入するFintech市場における現在の大きなトレンドは、「金融サービスの多様化」と「シームレス化」、この2つのキーワードに集約されるといっていいでしょう。
Fintechという言葉自体は、アメリカではインターネットが広く普及した2000年代から存在していました。日本でよく使われるようになったのは2015年頃のことです。
2010年代に入ってスマートフォンを1人1台所有するような時代になり、また2010年代半ば以降ブロックチェーンやAIといったテクノロジーが進化したことが、モバイル決済やスマートフォンを使った口座管理アプリなどのFintechサービスが生まれる背景となり、「金融サービスの多様化」が進みました。
さらに2017年に改正銀行法が施行されたことで、オープンAPIを介してネット上で展開されている多様な金融サービス同士を連携する「シームレス化」の波が広がります。例えば、それまで銀行でしか行っていなかった貸付や預金などの機能を切り出してサービス提供するFintech企業や、クラウド家計簿、クラウドファンディング、クラウドファクタリングなどのサービスが続々と生まれ、既存の金融機関とFintechベンチャーによるオープンイノベーションが、金融業界の景色を大きく変えつつあります。
金融機関のDX推進に求められるデジタル人材
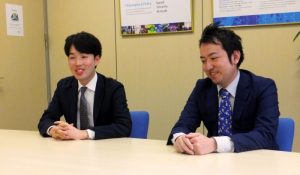
こうしたトレンドを背景に、ここ2、3年でFintech領域におけるデジタル人材の移動がある程度インパクトのある規模になってきました。
既存の金融機関、大手Web系プラットフォーマー、新興ベンチャーという大きな括りでそれぞれの人材採用のボリュームを比較すると、大手Web系プラットフォーマーが圧倒的に多い状況です。金融機関でもDXは進みつつあるものの、デジタル専門の組織がそこまで大きくないところがほとんどです。また、新興ベンチャーも採用を行っている企業数は多いですが、1社当たりの採用数は少ないため、比較すると大手Web系企業での採用が目立っています。
個別に見ていくと、既存の金融機関のDXは「社内向け」と「社外向け」に大別でき、どちらも注力の対象です。
「社内向け」のDXは、基本的には業務改善(BPR=Business Process Re-engineering)が主な目的となります。今は特に、RPA(Robotic Process Automation)による業務効率化・省力化が盛んです。既存のサービスのITによる自動化・効率化や、UI/UXの強化・改善なども「社内向け」のDXに含まれるため、UI/UXデザイナーなどを採用するケースも見られます。
また、社内システムの開発・運用にアジャイル開発やDevOpsといった手法を取り入れることで、よりスピーディにPDCAを回していくスタイルにIT部門の文化・体制ごと変革する動きが進んでおり、ベンダー管理ではなく自分で手を動かせるタイプのエンジニアが求められています。
一方「社外向け」のDXは、新しいビジネスの創出に重きを置いている企業が多いです。DX推進のための別会社を立てたり、社内にDX専任の組織を設け[HK1] て進めているケースが多いようです。
ある保険会社では、自動車業界を中心に進むMaaS(Mobility as a Service)が社会に普及した時の保険のあり方を検討しており、そのためにデータサイエンティストの採用に注力しています。また別の会社では、CVC(Corporate Venture Capital)ファンドを組成し、スタートアップに投資・協働しながら新規ビジネスの創出を模索する動きをとっています。
こうした新規ビジネス創出に伴う人材ニーズは高く、経験業種を問わず、ゼロから新規事業を立ち上げた経験がある人、あるいはITの技術的知見が豊富な人が重用される傾向があります。金融業界経験は問われません。ただ、求められる具体的な職種・経験・スキルは、どのようなビジネスを生み出そうとしているかによって異なり、BizDev、データサイエンティスト、エンジニアなど幅広いニーズがあります。
Web系プラットフォーマー・Fintechベンチャーに求められるデジタル人材
他方、“非金融業”からFintech領域に参入してきている大手Web系プラットフォーマーおよびFintechベンチャーにおける採用ニーズは、どのようなものでしょうか。
まず、Web系プラットフォーマーを見ていきましょう。先にお話ししたように、プラットフォーマーの採用熱は高く、また採用人数も多いです。求められる人材は、事業をつくる「ビジネス人材」と、実装する「システム人材」、その両者の間を通訳のような形で橋渡しする「ブリッジ人材」という、大きく3つの人材タイプに分けられます。
ビジネス人材・ブリッジ人材については、一部、金融機関経験者が求められるケースがあります。規制業種である金融業に参入する上では、金融庁の対応は避けて通ることができません。そのため、金融経験者、中でも実際に金融庁と折衝する立場にあったような経験豊富なミドル〜シニア人材が求められます。ただ、採用する全員がというわけではなく、数も多いわけではありません。
半面、システム系の人材──データサイエンティスト、UI/UXデザイナーなども含む──については、採用人数は多く、金融業界知識も必要とはされません。
また、ある程度成熟してきた事業において、企画・開発といった「攻め」の人材は足りているのですが、セキュリティ・監査などの「守り」のポジションが採用できていないことが多いため、そうしたニーズも出てきます。
新興のベンチャーにおいては、自社サービスを持っている事業会社の場合、システムは内製のところが多いため、エンジニアのニーズは高く、獲り合いの様相が強くなっています。特定の技術に長けたエンジニアや、フロントもバックエンドも見られるフルスタックエンジニアのニーズ、あるいはビジネスも技術も分かる人材といった高い要件が課されるケースが多いようです。
また、ブロックチェーンやAIなど、特定の分野のテクノロジーに特化し、金融機関やプラットフォーマーなどから案件を受託して技術を提供するタイプのFintechベンチャーも数多く出てきており、そこでもエンジニアのニーズは高い状況です。
ビジネス系のポジションについては、新規ビジネス開発に携わることになるため、Web系プラットフォーマー、あるいは他のFintechベンチャーで、新規事業を立ち上げた経験がある、社内外を巻き込んでビジネスを作っていける人が求められています。
デジタル人材採用にあたっての課題と打ち手

先にも少し触れましたが、金融機関では「イノベーションラボ」のような機能を別会社で立ち上げたり、社内にデジタル専門部署を設けたりして、DXを推し進めようとしている傾向にあります。
金融機関には歴史ある企業が多く、本業の成熟とともに組織としても確固たる制度や文化が確立しているため、新しいビジネスを創出しようとするとコンフリクトが起きる可能性があります。そのため、あくまでも本体とは「別」の組織とし、CDOとして役員を立ててその人が責任を持ってDXを推進するほうが、無用な軋轢を避けられるということがあるようです。
Fintech市場が拡大すればするほど、金融機関と“非”金融のWeb系企業・ベンチャー企業の間の人材流動は盛んになってきています。その際に、「成熟した組織」と「新興組織」、両者の間の大きすぎる文化的なギャップが、採用する上でのハードルになるケースはあります。
そうしたなか、金融機関でDXのための組織を別立てし、例えばベンチャーの多いエリアにオフィスを設けたり私服勤務を許可にしたり、あるいは組織の制度も本体とは別の体系をつくることで、そのギャップを埋めている様子がうかがえます。
「今までの組織はこうだったから」「今まではこういうやり方で採用してきたから」といった固定観念を取り払って、どうすれば求める人材を採用できるのかをゼロベースで考える柔軟な思考を持つことが、デジタル人材の採用成功につながるはずです。
IT業界の転職関連コンテンツ
IT業界の職務経歴書の書き方
- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】
- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説
転職サポート サービスの流れ
-
Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。
-
Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。
最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -
Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。
レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。
-
Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。
ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -
Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。